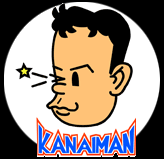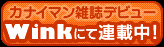Home > ESSAY > 第49話 「マトリョーシカ協奏曲」
第49話 「マトリョーシカ協奏曲」
僕の人生の中で、最も恥ずべき「失態」。
それは、あまりの忙しさに気を取られ、彼女の「誕生日」を忘れてしまった「事実」である。
言い換えれば、彼女を驚かせることが大好きな僕が、無意識に仕掛けた「最悪のサプライズ」という事になるのかもしれない。
一方、「記念日」という「恋人の儀式」には全く無頓着だったはずの彼女は、しばらくの間、声を押し殺し、冷徹な笑みを浮かべたままだった。
「あなたは、私の望みを全て受け入れなければならない。」
どれくらいの時間が過ぎてしまったのか覚えていないが、彼女はアルトのような低音域の声で、付き合って「初めてのサプライズ」を言い放ったが最後、次々と「報復」という名の「望み」を吐き出していく。
「旅行に連れて行くこと。」
「金曜日は会社を休んで、2泊3日で。」
「せっかくだから、アロマのエステもしてみたい。」
「ホテルは4つ星のジュニア・スウィートで、夜景が見えること。」
「日焼けは嫌だから、寒くもなく暑くもない所がいい。」
「旅のメイン・イベントは、クラシック鑑賞かな。」
「Mっ気」が強く、優柔不断の「女子力」しか持ち得ていない彼女は、「Sっ気」に溢れた僕の独断即決の「男子力」に、随分と魅かれていたはずなのに、今日は何だか、「イデオロギー」が逆転している。
そして、彼女は、マエストロの如く「欲望のタクト」を振り続け、意気揚々と「報復」を積み上げて行く。
果たして、彼女の条件を満たす「旅」の行き先など、この広い地球上に存在するのだろうか?
すると、いつの間にか笑顔になっている彼女は、ソプラノのような高音域の声で、「最後の望み」を解き放った。
「ウラジオストック」
彼女が選んだ「約束の地」は、ロシア極東部に位置する小さな港町。
新潟から飛行機で、たった1時間40分で辿り着くことのできる身近な海外だ。
僕と彼女は、初めてのロシア上陸に、いささか緊張しながらも、どこか懐かしい雰囲気の漂う「スヴェトランスカヤ通り」を散策した。
「ピロシキ」を頬張り、「ウオトカ」をゴクリ。
そして、ちょっとだけ顔を赤くした僕と、どこまでも色白の彼女は、街の楽団が奏でる「音楽」を鑑賞することに。
「ヴァイオリン協奏曲ニ長調」
チャイコフスキーが作ったこの名曲は、僕と彼女が初めてのデートで観た映画のワンシーンで流れていた思い出の楽曲。
それなのに、僕は、イントロから何度か繰り返されている熱狂的な「主題」の断片を聞いても、その「事実」に、まったく気付かず、第2楽章に入り、ソリストが力強く、その「主題」を独奏するまで、その「事実」を、すっかり忘れていたのだ。
一方、隣に座っている彼女は、声を押し殺し、冷徹な笑みを浮かべたままヴァイオリンの調べに身を委ねている。
「熱狂」と「冷徹」
「記憶」と「忘却」
ウラジオストックから帰国して、3日後。
彼女の「新たな報復」という名の「望み」を叶えるべく、僕は、彼女のマンションに向かっていた。
そう、あの「事実」から、さらに苛立っている彼女のために、「ラザニア」を僕が作らなければならないからだ。
そして、いつまでたっても合鍵を持たせてくれない彼女が、こっそりとスペアキーを隠している郵便受けを覗き込む。
そこには、「マトリョーシカ」が、ひとつ。
僕は、無表情の「マトリョーシカ」を手に取り、解体を始めた。
すると、またひとつ、まったく同じ「無表情」だけど、ちょっとだけ小さくなった色違いの「マトリョーシカ」が出てきた。
この物体の奥底に、彼女の扉を開く「鍵」があるのだと確信した僕は、またひとつ、またひとつと、徐々に小さくなっていく「マトリョーシカ」を、ひたすらに解体していく。
マトリョーシカが奏でる、「デクレッシェンド」。
そして、8体目になっても相変わらず無表情を続ける、とっても小さくなった「マトリョーシカ」を、ありったけの「希望」を込めて、パカッと開けた。
しかし、だ。
僕が、その存在を信じて疑わなかった、彼女へと続く「鍵」は、そこに、入っていなかった。
「希望」と「反逆」
「約束」と「革命」
ある音楽家は言いました。
「休符が記されていない楽曲など存在しない」、と。
五線紙には、「音」を奏でる「音符」ばかりが並んでいる訳ではない。
そこには、息継ぎのための「休符」があり、リズムを微調整する「休符」がある。
その何気ない「休符」の存在が、「熱狂」や「冷徹」、「希望」や「反逆」を表現し、「革命」の集大成として、「約束の地」へと共鳴させていくのだ。
もしかしたら、「音楽」とは、そんな「変化」を受け入れることなのかもしれない。
そして、その「変化」を受け入れるための「準備期間」として、「忘却」という名の「休符」を認めているのだろう。
つまり、「忘れること」は「罪」や「罰」ではなく、「変化までの休暇」と捉えることができるのかもしれないのだ。
再び、僕は、無表情の「マトリョーシカ」を手に取り、合体を始めた。
すると、またひとつ、まったく同じ「無表情」だけど、ちょっとだけ大きくなった色違いの「マトリョーシカ」が出来上がった。
僕は、またひとつ、またひとつと、徐々に大きくなっていく「マトリョーシカ」を、ひたすらに合体させていく。
マトリョーシカが奏でる、「クレッシェンド」。
そして、一番大きなマトリョーシカを合体させようと思った時、その大きな胴体の裏側に、「鍵」が張り付けてあることに気付いた。
「有る」と思い込んでいた所に無く、「無い」と思い込んでいた所に有る。
もしかしたら、この「事実」こそが、僕と彼女が奏でる「協奏曲」なのかもしれない。
「思い出」を重ねることで増える「音符」もあれば、「すれ違い」を繰り返しているうちに書き足される「休符」もある。
たとえ「リズム」が狂っても、たとえ「不協和音」が発生しようとも、僕たちの協奏曲は、「音符」と「休符」を繰り返しながら、いつまでもタクトを振り続けるのだ。
そして僕は、ひっそりとした彼女の部屋に入り、夕食の支度を開始。
彼女が帰って来るまで、残り20分。
BGMの「ヴァイオリン協奏曲ニ長調」は、第三楽章に入り、クライマックスの歓喜まで、ゆっくりと、ゆっくりと「クレッシェンド」が続いている。
そして、僕の想いも、だんだん大きくなっていく。